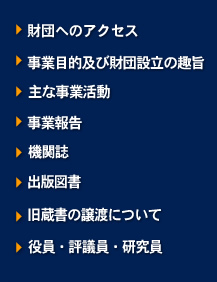海事交通研究(年報)総目次集
ご覧になりたい号のアイコンをクリックされると、該当の号の目次の部分に飛びます。
尚、各図書の目次の中の執筆者の肩書きは執筆当時のものです。
海事研究年報
第1号(昭和18年/1943年7月)
| 序 | 山縣勝見 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 我が統制経済に於ける海運統制 | 小島昌太郎 (京都帝国大学教授) |
|
| 明治海運史における国家と戦争 | 富永祐治 (大阪商科大学教授) |
|
| 海運政策に於ける中立貿易 -アメリカ海運政策論の分析- |
佐波宣平 (京都帝国大学助教授) |
|
| 海運原價について | 松本一郎 (当財団理事) |
|
| 【著書紹介】 | ||
| ドイツ景気研究所「海運に於ける競争」(1940年) | 佐波宣平 (前出) |
|
| 山戸嘉一箸「海事国際私法論」 | 折茂豊 (東北帝国大学法文学部助教授) |
|
| 海運関係文献解題(昭和17年) | 天野敬太郎 (京都帝国大学司書) |
執筆者紹介(掲載順)<原文通り転載>
小島昌太郎氏(我が統制經濟に於ける海運統制)
京都帝國大學教授、經濟學博士、「海運同盟論」「海運經濟要論」「海運賃率論」
「海運論」等海運に關する著述論文多く又「保險本質論」「保險業總論」等保險に
關する論著も尠(すくな)からず、最近は東亞金融問題に關する研究に專念せられて
居る。尚本財團の評議員である。
富永祐治氏(明治海運史における國家と戦争)
大阪商科大學教授、交通論專攻、「經濟學雑誌」其の他に研究發表多く、最近
「交通學の生成」なる交通學説史研究上の著書を公けにされた。尚本財團の研究
嘱託である。
佐波宣平氏(海運政策に於ける中立貿易)(ドイツ景氣研究所「海運に於ける競爭」紹介)
京都帝國大學助教授、小島博士の後を繼承して海運及保瞼講座を擔任(たんにん)
され、「經濟論叢」・「海運」誌上に多く研究論文を發表し「再保瞼の發展」邦譯
「シユターフェルド海運運賃市場」等の著述がある。尚本財團の研究嘱託である。
松本一郎氏(海運原價について)
辰馬汽船株式會社取締役常務理事其の他關係諸會社の重役を兼ね又本財團理事
である。曩(さき)に海運統制委員會、海運中央統制輸送組合幹事及船舶運營會
管理部長として海運統制の企劃(きかく)及實施に参劃(さんかく)し、「海運」に
研究論文の發表多く又近くは「南洋を中心とする東亞の海運」の研究報告がある。
折茂豊氏(山戸嘉一箸「海事國際私法論」紹介)
東北帝國大學法文學部助教授、「法學」「國際法外交雑誌」等に多くの研究論文の
發表がある。
天野敬太郎氏(海運關係文獻解題・昭和十七年)
京都帝國大學司書、「圖書目録法の研究」「論文總覧、正編、追編」「本邦書誌の
書誌」「圖書館總覧」等の著述がある。
改題・復刊:『海事交通研究』(年報)
第1輯(1965年11月)
| 復刊のことば | 山縣勝見 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 長期海上運送契約に関する一つの経済理論 | 佐波宣平 (京都大学教授) |
|
| 定期船市場における競争の一分析 | 前田義信 (甲南大学教授) |
|
| 徳川中・後期米穀海運企業史 | 松本一郎 (当財団理事) |
|
| 定期用船契約に関する立法例 | 窪田宏 (神戸大学教授) |
第2輯(1966年6月)
| 幕末・明治初期海運企業史 | 松本一郎 (当財団理事) |
|
|---|---|---|
| 港湾投資効果の判定 | 中西睦 (早稲田大学助教授) |
|
| 船舶の火災と海上保険および共同海損 | 亀井利明 (関西大学助教授) |
|
| 海上労働の特殊性と船員賃金 | 山本泰督 (神戸大学助教授) |
|
| 海運用役の供給曲線 | 山田浩之 (京都大学助教授) |
第3輯(1966年12月)
| イギリス港湾業の労務管理に関するメモ -ロンドン港における事情を中心として- |
地田知平 (一橋大学教授) |
|
|---|---|---|
| 港湾管理における英米両方式の得失について | 高村忠也 (神戸大学教授) |
|
| 西ドイツ内航海運に関する一考察 | 秋山一郎 (神戸大学助教授) |
|
| 世界海上荷動きの変遷と不定期船海運業 | 松本一郎 (当財団理事) |
第4輯(1968年3月)
| 英文海上保険証券の解釈原則 -Ivamy著 General Principles of lnsurance Law(1966)と拙著「海上保険研究」(昭和24年)との比較- |
葛城照三 (早稲田大学教授) |
|
|---|---|---|
| 欧州貨物交通事情 -B.T.Bayliss箸 European Transport の紹介- |
野村寅三郎 (神戸大学名誉教授) |
|
| ニューヨーク ポート・オーソリテイー |
増井健一 (慶応義塾大学教授) |
|
| 古記録より見たる古代・中世前期の海商及び海運企業活動 |
松本一郎 (当財団理事) |
|
| H.Sanmannの海運市場論 |
鈴木繁 (立正大学助教授) |
第5輯(1969年5月)
| 三十歳を迎えて(1940~1969) |
松本一郎 (当財団理事) |
|
|---|---|---|
| わが国に於ける造船技術近代化の源流 |
加地照義 (神戸商科大学教授) |
|
| 先物長期運賃水準と予想 |
下條哲司 (神戸商船大学助教授) |
|
| 1966年英国港湾法の制定について |
織田政夫 (東京商船大学助教授) |
|
| ドイツ海運史の一断面 -A・バリンとハンブルク・アメリカライン- |
鈴木孝明 (大東文化大学講師) |
|
| オイディナミッシェビランツの理論的構造 |
高木泰典 (高千穂商科大学講師) |
第6集(1970年3月)
-創立30周年記念特集号-
| 30周年記念特集号の発刊に際して |
山縣勝見 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 海運経済学の成立 |
小島昌太郎 (京都大学・神戸商科大学各名誉教授) |
|
| 交通政策とその総合性 |
島田孝一 (早稲田大学名誉教授) |
|
| 「外観良好」文句と「中味不知」文句に関する最近の判例について |
小町谷操三 (東北大学名誉教授) |
|
| 国際紛争と海商対策 |
石津漣 (九州産業大学長) |
|
| 海運における近代化とその影響 |
麻生平八郎 (明治大学教授) |
|
| 国際連絡運輸制度の提唱 |
高橋秀雄 (流通経済大学教授) |
|
| 船舶保険普通約款の若干の問題点 |
葛城照三 (早稲田大学教授) |
|
| 黄金と国際経済 |
関野唯一 (独協大学教授) |
|
| 中世後期地中海・北海海運企業史論究 |
松本一郎 (当財団理事) |
|
| 財団法人山縣記念財団の沿革 |
古川哲次郎 (当財団) |
第7集(1971年10月)
| 辰馬海運百五十年経営史資料篇 |
松本一郎 (当財団理事) |
|---|
第8集(1972年5月)
辰馬海運百五十年経営史
| 序 |
山縣勝見 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 本文 |
松本一郎 (当財団理事) |
第9集(1973年6月)
|
海運経営における予測・決定・計画へのアプローチ -ベルゲン・セミナーの印象- |
下條哲司 (神戸商船大学助教授) |
|
|---|---|---|
| 十六世紀東西海上交通時代の海商活動 |
松本一郎 (当財団理事) |
第10集(1974年7月)
| 十七世紀和蘭海運貿易企業史研究 |
松本一郎 (当財団理事) |
|
|---|---|---|
| 日本海運企業の油濁責任と保険革新 |
来住史郎 (日本船舶責任相互保険組合) |
|
| 石油危機・船舶関係資料 |
松本一郎 (前出) |
第11集(1975年3月)
| 我国損害保険会社の保証事業進出について | 井筒享 |
|---|
第12集(1975年10月)
| 十六世紀(エリザベス女王時代)十七世紀(クロムウェル時代)英国海運企業史研究 |
松本一郎 (当財団理事) |
|
|---|---|---|
| 食糧危機と海上輸送 |
高田富夫 (早稲田大学大学院博士課程) |
第13集(1976年6月)
| 17・18世紀英国東方貿易海運企業史・英国東印度会社 海運経営研究 |
松本一郎 (当財団理事) |
|
|---|---|---|
| 英国港湾機構概説 |
織田政夫 (東京商船大学助教授) |
第14集(1977年5月)
| 故山縣勝見理事長追悼之記 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 17・18世紀前期英国,仏国抗争期における海運企業研究 |
松本一郎 (前出) |
|
| 世界経済の発展と船腹需要 -1950~73年の構造分析- |
高田富夫 (当財団研究員) |
第15集(1978年4月)
| 船員の共同雇用制をめぐる若干の問題 -イギリスの制度を中心にして- |
地田知平 (一橋大学教授) |
|
|---|---|---|
| 海運における経済効率-Gossの論文に寄せて- |
東海林滋 (関西大学教授) |
|
| 17・18世紀および19世紀初期英仏海運企業史研究補遺 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
| わが国海運国際収支の実証的研究 |
山岸寬 (東京商船大学助教授) |
|
| 15世紀明時代鄭和・南洋-印度洋航海記中国語・英語・日本語訳本に就て | 木下文和 |
第16集(1979年5月)
| 故小島・小町谷両評議員追憶の記 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 英米戦争(1812年)前後海運業研究 |
松本一郎 (前出) |
|
| ルードルフ・ヴァーグナー小伝 |
窪田宏 (神戸大学) |
|
| 二大定期船会社の創立-郵・商二社の設立過程- | 加地照義 |
第17集(1980年3月)
| 19世紀初期アメリカ海運業太平洋・東洋活動状況の 研究 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 南太平洋の大国オーストラリヤ(Terra Australis-豪州)十九世紀前期の貿易海運企業史研究 |
松本一郎 (前出) |
|
| 英米の船員雇用制度と雇用調整および技術革新への適応 |
山本泰督 (神戸大学) |
|
| 試練に立つ中小船社 |
國領英雄 (神戸商船大学) |
|
| イタリア法上の「仲裁条項」に関する若干の問題(覚書) |
今井薫 (駒沢大学) |
第18集(1981年2月)
| アフリカ大陸大西洋岸・印度洋岸海運業研究 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 嵐の中のわが国同盟船社 |
高村忠也 (神戸大学教授) |
|
| 主要経済指標及び海上荷動量の趨勢 |
今橋宏 (山下新日本汽船) |
|
| 十九世紀初期ロシヤ船の日本経由世界周航記につ いて |
松本一郎 (前出) |
|
| 新刊海運史書紹介 |
松本一郎 (前出) |
|
| ナポレオン皇帝敗退後の仏英軍事力及び経済状況について(コブデン報告に基く資料) | 前山松郎 |
第19集(1981年12月)
| 創立四十周年を迎えて |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| コンテナ船海運経営上の諸問題 |
前田義信 (甲南大学) |
|
| スペース・チャーター方式の現代的意義 |
窪田宏 (神戸大学) |
|
| コンテナ国際物流システムの評価 |
下條哲司 (神戸大学) |
|
| コンテナリゼーションと港湾-その対応と経営状況- |
國領英雄 (神戸商船大学) |
|
| コンテナ船埠頭荷役及び諸設備の合理化について |
三木楯彦 (神戸商船大学) |
|
| 東アジア貿易史研究展望 |
杉山伸也 (ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス) |
|
| 希望峰巌頭に立って大航海者を想う |
松本一郎 (前出) |
第20集(1982年6月)
| 古代・中世船商資本の調達について |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 第二次大戦後におけるアメリカの海軍力 -レイノルズの論文をめぐって- |
山本泰督 (神戸大学) |
|
| 独立後のインド経済動向と海運業 |
黒沢晃 (松蔭女子学院大学) |
|
| 大航海者マゼラン死後-比律賓・太平洋海域の海商活動(金銀財宝船のSilver Galleon Fleet状況) |
松本一郎 (前出) |
|
| 資料I P.B.ブウシェの(中世海法)「コンソラート・デル ・マーレ」のこと(紹介) |
窪田宏 (神戸大学) |
|
| 資料Ⅱ アメリカに於ける労働力,構成,賃銀問題の変 化と海運業 |
大瀬戸省作 (京都大学) | |
| 資料Ⅲ 英国東印度総督ベンチック伝記(印度洋蒸汽 船就航問題) |
I.M. |
第21集(1983年3月)
| 幕末・明治維新における軍艦・商船取得及び外国知識に関する動向について |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| バルク・カーゴ積み取り調整についての一考察 |
高村忠也 (神戸大学) |
|
| 【特別レポート】 | ||
| オックスフォードとオックスフォード大学 |
山田浩之 (京都大学) |
|
| 【資料】 | ||
| ロンドン大学の機構と研究機関 |
杉山伸也 (ロンドン大学) |
|
| 1983年の海上運賃市況は乾油いづれの部門が先に回復に向うかについての一考察(エネルギー・コストの競合を視点として) |
今橋宏 (神戸マリンターミナル) |
第22集(1983年10月)
| イスパニヤ海運業衰退の過程 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 清代前期中国・英国間海運貿易研究 |
松浦章 (関西大学) |
|
| 韓国船員事情管見 |
國領英雄 (神戸商船大学) 陶怡敏 (神戸大学大学院) |
|
| 〔資料I〕 13世紀アドリア海におけるベネチヤ海上貿易と護衛船について |
松本一郎 (前出) |
|
| 〔資料Ⅱ〕 ミシェル モラ箸「海事史研究」論集 |
窪田宏 (神戸大学) |
|
| 〔資料Ⅲ〕 マーンリオ コルテラッツォ監集「地中海と印度洋(第6 回海事史学会報告)」 |
窪田宏 (前出) |
|
| 〔資料Ⅳ〕 ポルトガル・中国通商海運史資料について -張天澤『中葡通商研究』を中心に- |
福田和則 |
第23集(1984年3月)
| 英国航海条例と北米合衆国独立史 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 「香港」の将来 |
下條哲司 (神戸大学教授) 吉田茂 (神戸商船大学) |
|
| 16-19世紀の中国・フィリピン間の海上貿易 |
松浦章 (関西大学) |
|
| 【紹介】 | ||
| 海運投資時機の適合 |
今橋宏 (神戸マリンターミナル) |
第24集(1984年8月)
| 18・19世紀初期支那・アジア南方地域に於ける船商活動 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| インドの海運事情と政府の海運助成政策 |
黒沢一晃 (松蔭女子学院大学教授) |
|
| 台湾の海運・造船政策に関する一考察 |
陶怡敏 (神戸大学大学院) |
|
| 【資料】 | ||
| (1)老頭児,船長,社長語り草 (2)近畿四国,瀬戸内出身船主・船長の人々 (3)四国出身社外船主の雄 |
松本一郎 (前出) |
第25集(1985年3月)
| 古代ギリシア及びローマ時代・海運事業の研究 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 近代前の中国海船の資本調達について |
松浦章 (関西大学) |
|
| 「回船大法」フィールド・ノート -海事社会とその慣習を求めて- |
窪田宏 (神戸大学) |
第26集(1985年9月)
| 中近東トルコ発展期に於ける海運業研究 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 北米定期航路の競争と主要船社の対応 |
今橋宏 (神戸マリンターミナル) |
|
| ウェールズ大学と海運の研究 |
山岸寬 (東京商船大学) |
第27集(1986年2月)
| 印度洋の海運業史考 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 米国駐在の目から見たコンテナ海陸一貫輸送の展開 |
山中洋 (本名:竹ノ内豊司) |
|
| 欧州海運諸国を訪問して |
山岸寬 (東京商船大学) |
|
| 北欧海運会社の活躍 |
今橋宏 (神戸マリンターミナル) |
第28集(1986年10月)
(創立四十五周年記念号)
| 財団法人山縣記念財団発足45周年(実働40年)に際して |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 創立45周年記念祝賀会挨拶 |
松本一郎 (前出) |
|
| 創立45周年記念祝賀会祝辞 |
麻生平八郎 (元明治大学総長) |
|
| 創立45周年記念祝賀会乾杯の音頭 |
山下三郎 (山下新日本汽船相談役 海事産業研究所理事長) |
|
| 太平洋航路半世紀後・コンテナー船時代の最近の現状を訪ねて |
松本一郎 (前出) |
|
| 【参考文献】 | ||
| アメリカ大陸横断鉄道小史及びトラック輸送状況 |
松本一郎 (前出) |
|
| 欧州主要国の海運政策の基調と問題点 |
山岸寛 (東京商船大学) |
〔資料I〕
世界的石油政策・石油価格の動向に関するIEA(International Energy Agency)主席理事Aelge Steeg氏,及びW.Hopkins氏の見解(OECD observer l986-5月号所裁概要)
〔資料Ⅱ〕シンガポール動向・石油に関する最近の統計
〔資料Ⅲ〕米西海岸に於て鉄道とコンテナーの連結進む
〔資料Ⅳ〕1984年米国海運法
財団年表
第29集(1987年3月)
| 南太平洋航路配船半世紀 |
松本一郎 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 中国・唐宋時代及び古代ギリシャの海上取引賃借について |
松本一郎 (前出) |
|
| オフショア登録と船舶管理業 |
山岸寬 (東京商船大学) |
|
| 日清戦争前における日本海運の近海進出 -領事報告に見る諸相- |
片山邦雄 (神戸商科大学商経学部) |
|
| ソ連海運の概況 |
杉崎恒雄 (東洋共同海運) |
【付属資料】
Iソビエト海運政策の変更
Ⅱソ連海運の脅威は誇張されている
第30集(1987年9月)
| 明治20年代中期の航路拡張論 -『日本海運論』を中心として- |
片山邦雄 (神戸商科大学) |
|
|---|---|---|
| 『交通業の垂直型多角化の戦略的意義』 |
吉田茂 (神戸商船大学) |
|
| 印度海運造船の現況 |
近藤美作 (本名・旦延繁元山下新日本汽船) |
|
| ソ連の海運の現況 |
杉崎恒雄 (東洋共同海運) |
【資料】香港World Wideの動静
第31集(1988年3月)
| オフショア海運とコスト分析 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
|---|---|---|
| Intermodal Competitionにおけるセカンド・ベスト価格 |
吉田茂 (神戸商船大学助教授) 橋本健司 (神戸商船大学大学院生) |
|
| 中国廣州事情 |
三ツ井光晴 (神戸商科大学助教授) |
第32集(1988年9月)
| 現代の外航海運像 |
織田政夫 (東京商船大学教授) |
|
|---|---|---|
| 海運業の成長構造 |
高田富夫 (名古屋学院大学経済学部教授) |
|
| 海運企業における戦略的課題-日本海運企業を中心に- |
吉田茂 (神戸商船大学助教授) |
第33集(1989年6月)
| 現今内航海運市場の特殊相 |
國領英雄 (神戸商船大学教授) |
|
|---|---|---|
| 海運費用の構造とマンニング・コストの特殊性 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| 運輸業における情報ネットワークシステム |
吉田茂 (神戸商船大学助教授) |
|
| イギリス法「1930年第三当事者法(保険者に対する権利)」にもとづくP&Iクラブに対する直接請求に関する若干の問題 -控訴審判決を事例として- |
Capt.K.Saito (日本船主責任相互保険組合) |
第34集(1989年12月)
| EC船籍(EUROS)の設立に関するパッケージ案の概要 |
織田政夫 (東京商船大学教授) |
|
|---|---|---|
| 市況予測と海運循環 |
國領英雄 (神戸商船大学教授) |
|
| 海運の構造転換とフラッギング・アウト対策 -英国海運を中心として- |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| 海上輸送の技術進歩と海運産業の規模 |
高田富夫 (名古屋学院大学教授) |
|
| 交通企業の組織構造 |
吉田茂 (神戸商船大学助教授) |
第35集(1990年6月)
| 内航船員問題の現状分析と若干の試論 |
織田政夫 (東京商船大学教授) |
|
|---|---|---|
| 米国海運政策考-続・船舶建造融資保証制度- |
國領英雄 (神戸商船大学教授) |
|
| 船舶管理の需給構造と経済現象 |
山岸寛 (東京商船大学教授) |
|
| 交通業の規制緩和とその効果 |
吉田茂 (神戸商船大学助教授) |
第36集(1990年12月)
| 定期船会社の企業行動と市場の特殊性 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
|---|---|---|
| 海上輸送市場の活動分析型生産関数 -生産関数による技術進歩分析序説- |
高田富夫 (名古屋学院大学教授) |
|
| 「I.T.F/FOCキャンペーンと米国海運法第10313条(46USC§10313)」 -アメリカ判例”Fareast Trader”号事件(l989AMC2721)を事例として- |
Capt.K.Saito (日本船主責任相互保険組合) |
第37集(1991年6月)
| 途上国船員の労務管理 |
山本泰督 (神戸大学教授) |
|
|---|---|---|
| 韓国海運見聞記 |
織田政夫 (東京商船大学教授) |
|
| フラッギング・アウトの構造とその受入れ国の経済的役割 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| ローマ条約競争規定と海運のコンソーシアム -一括適用除外問題を中心として- |
松本勇 (長崎県立大学教授) |
第38集(1991年12月)
| 物流政策のなかの内航海運-モーダルシフトの可能性をめぐって- |
國領英雄 (神戸商船大学教授) |
|
|---|---|---|
| 国際海運の構造転換とその現代的特質 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| 海運経済のインハウスデーターベース -一つの統合型管理システムの提案- |
高田富夫 (名古屋学院大学教授) |
|
| 海運企業における事業の多様化と成長性 |
吉田茂 (神戸商船大学助教授) |
第39集(1992年6月)
| 日本人船員保有の必要性とそのフィージビリテイ |
山本泰督 (神戸大学教授) |
|
|---|---|---|
| 海運市況の循環構造 |
國領英雄 (神戸商船大学教授) |
|
| 第3型海運の存立意義と政策的実践 -スカンジナビア諸国を中心として- |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| 複合一貫輸送とEC競争規定の適用除外 |
松本勇 (長崎県立大学教授) |
第40集(1992年12月)
| 国際交通業の産業組織の変質-規制緩和政策の実証分析- |
宮下國生 (神戸大学教授) |
|
|---|---|---|
| 先進国の海運の再建と問題点-ギリシャ海運を中心として- |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| 海運経済数量分析のためのコンピュータソフトウエア -データベース構築の方法と数量分析のサンプルスタディ(1)- |
高田富夫 (名古屋学院大学教授) |
第41集(1993年6月)
| 国際運輸労連のTCC協約とベンチマーク |
山本泰督 (神戸大学教授) |
|
|---|---|---|
| 長距離フェリーのネットワーク形成と効果 |
國領英雄 (神戸商船大学教授) |
|
| コアの理論の海運市場分析への適用 -Pirrong論文の紹介と検討- |
杉山武彦 (一橋大学教授) |
|
| 海運経済数量分析のためのコンピュータソフトウエア -データベース構築の方法と数量分析のサンプルスタディ(2)- |
高田富夫 (名古屋学院大学教授) |
第42集(1993年12月)
| 草創期の海運計量分析-故松本一郎氏の先駆的業績を偲ぶ- |
下條哲司 (甲南大学理学部経営理学科教授) |
|
|---|---|---|
| 海運政策の限界-若干の海運政策論の検証- |
織田政夫 (東京商船大学教授) |
|
| 海運サービスにおける品質管理の国際規格 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| EC海運競争規定と欧州ゾーンチャージ |
松本勇 (長崎県立大学教授) |
第43集(1994年6月)
| JSU/AMOSUP労働協約について |
山本泰督 (神戸大学名誉教授) |
|
|---|---|---|
| 海上輸送誘導のための一つの試算 |
國領英雄 (神戸商船大学教授) |
|
| オープン登録の意義と検証 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| 港湾施設の価格形成 -T.J.Dowd論文の紹介および検討- |
杉山武彦 (一橋大学教授) |
第44集(1995年11月)
| 中国の市場開放と海運活動 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
|---|---|---|
| 海運のコンソーシアム協定に対する一括適用除外規則870/95の行方 |
松本勇 (長崎県立大学教授) |
|
| 国際海運における伝統的海運国の位置に関する一考察 |
高田富夫 (名古屋学院大学教授) |
第45集(1997年1月)
| 海運諸問題の始発的動因としての国内環境条件 |
織田政夫 (東京商船大学教授) |
|
|---|---|---|
| 国際物流業のサービス差別化戦略 -ロジステイクス・システム革新への対応- |
宮下國生 (神戸大学教授) |
|
| EU海運政策と競争法-その政策目的と競争法の運用- |
松本勇 (長崎県立大学教授) |
第46集(1997年11月)
| 海上安全とポートステート・コントロール |
織田政夫 (流通経済大学教授・東京商船大学名誉教授) |
|
|---|---|---|
| アジアの対米物流構造の機能メカニズム |
宮下國生 (神戸大学教授) |
|
| わが国海運の再建と国際船舶制度の創設 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| 需給調整規制の廃止と離島航路政策に関する一考察 |
松本勇 (長崎県立大学教授) |
第47集(1998年10月)
| 海運産業の成長と存続の条件 |
織田政夫 (流通経済大学教授・東京商船大学名誉教授) |
|
|---|---|---|
| アジア物流と日本の拠点港湾の行動メカニズム |
宮下國生 (神戸大学教授) |
|
| EUにおけるフラッギング・アウトの動向と海運助成策 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
|
| 中国海運業と海運政策のあり方 |
吉田茂 (神戸商船大学教授) 全賢淑 (大連海事大学院生) |
第48集(1999年10月)
| 国際運輸労連(ITF)のFOCキャンペーンについて -労働組合の国際的連帯とその課題- |
山本泰督 (南大阪大学) |
|
|---|---|---|
| わが国における為替変動と海運企業の経営行動 |
山岸寬 (東京商船大学教授) 詹詠梅 (ワールドマリン㈱) |
|
| 日本海運業の競争力形成とその変容 -定期船海運を中心にして- |
吉田茂 (神戸商船大学) |
|
| 国際定期船海運のコンソーシアムに対する委員会規則第870/95の改正とその問題点 |
松本勇 (長崎県立大学教授) |
第49集(2000年10月)
(財団設立60周年記念号)
| ~はじめに~ 当財団創立六十周年の節目に想う |
一樋宥利 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 海運経済学からの知的派生物 |
下條哲司 (大阪産業大学教授) |
|
| 東アジア発展回廊としての海上輸送システム |
國領英雄 (大阪学院大学教授) |
|
| アジアの対米物流構造とロジスティクス戦略拠点の構築 |
宮下國生 (神戸大学教授) |
|
| 競争優位とロジスティクス |
高田富夫 (流通経済大学教授) |
|
| 日本籍船間題をめぐる外航海運政策の理論的検証 |
澤喜司郎 (山口大学経済学部教授) |
第50集(2001年10月)
| わが国経済の蘇生と復活の道は? ~「門外漢」としての素朴な疑問と着想~ |
一樋宥利 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 東京商船大学における物流教育 |
杉崎昭生 (東京商船大学学長) |
|
| ターミナル文化の歴史と環境 |
北見俊郎 (青山学院大学名誉教授・北見港湾総合研究所長) |
|
| 海事クラスターの概念とその周辺 ~概念と産業政策上の意義についてのノート~ |
杉山武彦 (一橋大学教授) |
|
| サブスタンダード船はなくなるか ~船舶海難防止の取組に関する-考察~ |
織田政夫 (流通経済大学教授) |
第51集(2002年10月)
| “インフラストラクチャー” 関連事業に於る「公共性・ 公益性」と「民営化」の撞着について ~「官民共同」と「民活」とのさらなる融合の道を~ |
一樋宥利 (当財団理事長) |
|
|---|---|---|
| 海事社会における人材育成 ~これからの神戸商船大学~ |
原潔 (神戸商船大学長) |
|
| CENSA(欧州・日本船主協会評議会)38年の歴史とJSA(日本船主協会)(1) ~民間国際海運調整機関が国際定期船海運政策に与えた影響~ |
松本勇 (長崎県立大学教授) 赤塚宏一 (日本船主協会) |
|
| 米国シーランド社の企業行動とその史的展開 |
山岸寬 (東京商船大学教授) |
第52集(2003年11月)
| 戦後日本海運業の自立と海運政策 ~企業集中を中心とした戦後日本海運史の一節~ |
地田知平 (一橋大学名誉教授) |
|
|---|---|---|
| アジアにおける海上交通の安全確保のための国際協力について ~マラッカ海峡をめぐる最近の海洋法問題から~ |
栗林忠男 (慶應義塾大学名誉教授・東洋英和女学院大学教授) |
|
| 東アジアにおけるアライアンス形成前後のコンテナルート ネットワーク構造の変化について |
吉田茂 (神戸商船大学教授) 金広煕 (神戸商船大学博士課程) |
|
| 参考メモ “想春だより”(第1号~第11号)目次総括 |
一樋宥利 (当財団理事長) |
第53集(2004年11月発行)
| 【特別寄稿】 | ||
|---|---|---|
| 株式市場から見た海運業界 |
尾坂拓也 (野村證券(株)金融研究所企業調査部アナリスト) |
|
| 【海運の歴史】 | ||
| 日本海運の高度成長の成果 |
地田知平 (一橋大学名誉教授) |
|
| 【海運の直面する課題】 | ||
| わが国内航海運の現状 |
織田政夫 (流通経済大学流通情報学部教授) |
|
| わが国外航商船の第二船籍制度 |
山岸寬 (東京海洋大学海洋工学部教授) |
|
| 【新しい視点から】 | ||
| 国際経済環境の変化とわが国外航定期船海運業にお ける水平的企業結合の形成:事例研究とソロー残差の 計測をふまえて |
遠藤伸明 (東京海洋大学海洋工学部助教授) |
|
| 港の世界:人間と教育 ~若者の人材育成事情とその基本的課題に関連して~ |
富田功 (港湾職業能力開発短期大学校横浜校講師) |
|
| 多地域応用一般均衡モデルによる貿易予測と海運政策の影響評価 |
石黒一彦 (神戸大学海事科学部講師) |
|
| 【追悼】 | ||
| 故前田義信先生を悼む |
下條哲司 (元神戸大学教授前山縣記念財団監事) |
|
| 執筆者紹介 |
第54集(2005年12月発行)
| 【特集】 | ||
|---|---|---|
| 若き海運研究志望者へ:(社)日本船長協会刊「海運研究者の悲哀」(昭和26年)所収)の復刻掲載 |
佐波宣平 (元京都大学教授・故人) |
|
| 【特別寄稿】 | ||
| 「子供達に海と船を語る」企画について |
池上武男 ((社)日本船長協会技術顧問) |
|
| 石油危機後の日本海運~企業集中に向かって~ |
地田知平 (一橋大学名誉教授) |
|
| Globalizationと船舶融資 ~計画造船から貿易物資安定供給融資へ~ |
原田輝彦 (日本政策投資銀行設備投資研究所主任研究員) |
|
| 海事社会の基盤整備~主として海技技術者に関する人材基盤~ |
杉崎昭生 (東京商船大学名誉教授東京海洋大学名誉教授) |
|
| 海事教育の歴史と変遷~これからの人材育成の行方~ |
井上欣三 (神戸大学海事科学部教授) |
|
| 港湾の部分的な民営化が港湾管理に与えた影響 ~ランドロード型港湾における公共部分の役割~ |
寺田英子 (広島市立大学国際学部教授) |
|
| 太平洋戦争期の船舶運航と港湾 |
古川由美子 (一橋大学大学院経済学研究科ジュニアフェロー) |
|
| 執筆者紹介 |
第55集(2006年12月発行)
第56集(2007年11月発行)
第57集(2008年11月発行)
2008年山縣勝見賞決定